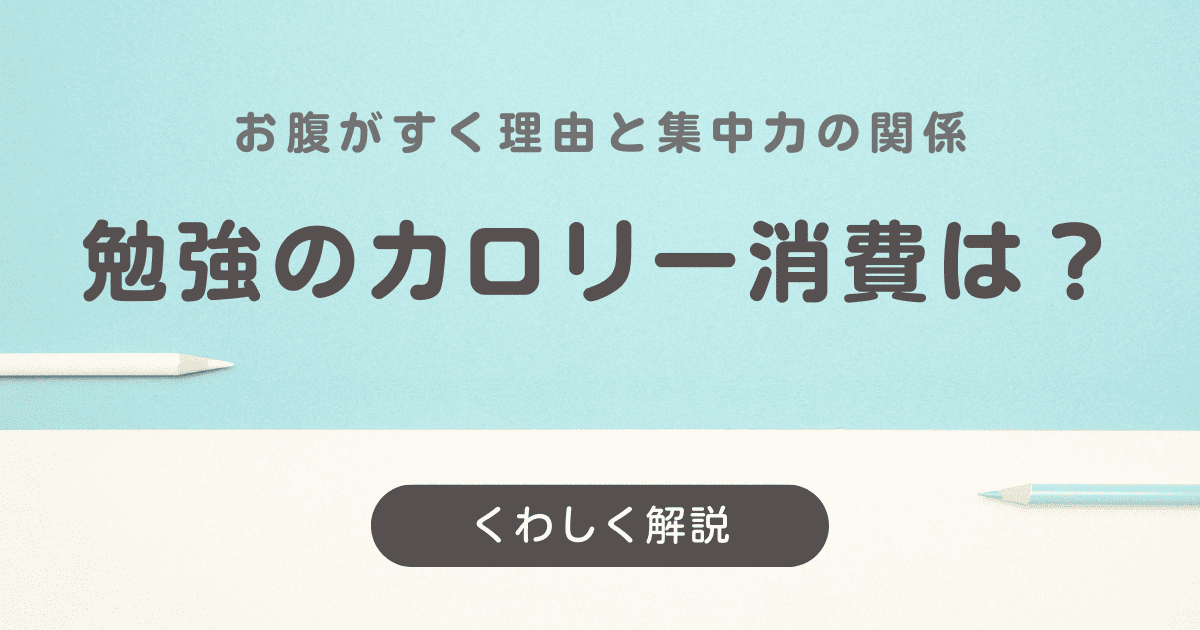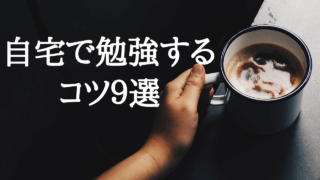勉強していて無性にお腹が空いた経験は、誰にでもあるでしょう。こんなに頭を使っているのだから、さぞかしカロリーを消費しているだろうし、もしかしてダイエット効果もあるのでは?と期待する方もいるかもしれません。
実際に人間の脳は、体重の2%ほどの重さにも関わらず、体全体の20%ものカロリーを消費しているといわれます。さらに成長期の中学生・高校生では、大人よりも多くのカロリーを脳で使っているのです。
しかし、勉強でダイエットできるかというと、残念ながら話は別です。この記事では、勉強で消費されるカロリーを具体的に計算し、お腹が空く意外な理由や、体重を気にする方が行える工夫をお伝えします。集中力を維持するための工夫も紹介しますので、ぜひ役立ててください。
勉強でのカロリー消費は意外と少ない!運動や食事に換算すると?

アメリカでの研究によると、中学生が1日に脳で消費するカロリーは、男子が約530kcal、女子が約470kcalです。ブドウ糖に換算すると115~135g、小さめのおにぎりなら約3個に相当するカロリー量です。
高校生では中学生よりも消費量が減っていき、19歳以上の成人になると、おにぎり2個分ほどのカロリー消費(約320~355kcal)で安定します。
一方で、勉強で脳を酷使しても、消費カロリーはさほど増えないとの報告もあります。勉強中には、実際どれくらい消費されるのでしょうか?
勉強で消費するカロリーはどれくらい?

2時間勉強する場合の消費カロリーを計算してみましょう。
まず脳の消費カロリーです。勉強中の消費量の上乗せは、多くても5%程度といわれています。脳は、複雑な神経ネットワークの維持管理に大量のエネルギーを必要とする一方、思考に要するエネルギーはわずかだというのです。
脳の消費カロリーを480kcal/日として考えると、1時間あたりの消費量は20kcalです。勉強中は5%増加し、2時間で21kcal消費する計算です。これは飴玉1個程度のカロリーです。
体全体の消費カロリーはどうでしょう。勉強中は座った姿勢を維持したり、書き取りで手や腕を動かしたりして、筋肉もカロリーを消費しています。
勉強中の全身の消費カロリーは、厚生労働省による運動量の計算式から割り出せます。活動の強さを表すMETs(メッツ)という数値を使い、「メッツ×活動時間×体重(kg)」と計算します。(中学生・高校生の消費カロリーは成人よりも多めですが、目安として利用できます)
座っての勉強は1.5メッツです。体重50kgとして計算すると、1.5メッツ×2時間×50㎏となり、2時間で150kcal消費することになります。
消費カロリーを運動・食事に換算すると?

座って2時間勉強したときの全身の消費カロリーは、運動に換算すると、以下と同程度です。
- 速めのウォーキング(4.3メッツ) 約42分
- ゆっくりジョギング(6.0メッツ) 約30分
- 野球(5.0メッツ) 約36分
- サッカー(7.0メッツ) 約26分
- 水泳(速くないクロール)(8.3メッツ) 約22分
体重が違っても、同じ人なら同じ換算となります。
また、食べ物に換算すると、およそ以下の量です。
- おにぎり 1個
- 食パン 6枚切り1枚
- バナナ1本+牛乳1/3杯
- 菓子パン 半分
- ポテトチップス小袋 1/2袋
こちらは体重や基礎代謝量で誤差が出ますが、中高生なら体重が軽めでも、基礎代謝は多めなので、相殺されると考えても大きな問題はありません。
勉強はダイエットには非効率

2時間勉強しても、体全体で150kcal、脳では21kcalしか消費しないと聞くと、意外と少なく感じる方も多いのではないでしょうか。勉強で消費するカロリーは、間食で簡単に相殺される程度の量です。残念ですが、勉強だけで体重を減らすのは現実的ではありません。
では、勉強しながら効率的にダイエットできる方法はあるのでしょうか。おすすめは、休憩時間の運動です。勉強の前や後に運動することで、空腹感やおやつの摂取量が抑えられた、との研究がいくつも報告されています。
もちろん運動によるカロリー消費もダイエット効果があります。以下に休憩中に簡単にできる運動とメッツ数を挙げました。
- ストレッチ 2.3
- ほどほどの強度の筋トレ 3.8
- 早歩き 4.3
- スクワット 5.0
- ジョギング 7.0
- 強い強度の筋トレ 8.0
- 階段を速く上る 8.8
- ランニング(分速140m程度) 9.0
静かに座って休憩する場合(1.0メッツ)と比べると、軽い運動でも2倍以上のカロリーを消費できる計算です。学校や塾の行き帰りに早歩きするだけでも消費カロリーが違ってくるため、ぜひ試してみてください。
でも勉強したらお腹が減る!カロリー消費以外の理由とは

「運動ほどカロリーを消費しないのに、なんでこんなにお腹がすくの!?」と納得できない方もいるかもしれません。勉強でお腹が空く理由の一つに、自律神経の切り替わりが考えられます。
集中しているときは、体を緊張状態にさせる交感神経が優位で、食欲を感じにくい状態です。しかし集中が切れると、リラックスを担当する副交感神経が優位になります。すると胃腸が活発に動き出し、どっと空腹感に襲われることがあるのです。
また、脳の主なエネルギー源はブドウ糖です。集中して考えつづけ、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)がわずかに下がると、変化を脳が敏感にキャッチします。そして空腹を感じさせるサインを出すことで、お腹が空いた感じがしてきます。
さらに最近の研究で、脳は乳酸もエネルギー源とすることが分かってきました。たとえば勉強後に強めの運動をして、筋肉で乳酸が作られると脳へも届き、ブドウ糖不足が相殺されると考えられるのです。体をあまり動かさないと乳酸が供給されず、ブドウ糖だけが減っていくため、脳はエネルギー不足を感じやすいかもしれません。
このように神経の働きや、血液中のブドウ糖・乳酸の量などさまざまな要因によって、勉強による空腹感が生まれると考えられます。
集中力を保つ!勉強中のカロリー消費と付き合う休憩・補給法
量としては少なくても、勉強中の脳はカロリーを消費し続けています。効率よく集中を保つには、こまめな休憩や適切なエネルギー補給が欠かせません。ここでは、勉強と上手に付き合うための休憩法やおやつの工夫を紹介します。
軽く体を動かして脳をリフレッシュ

長時間座って勉強を続けていると、脳に酸素が届いていないような感覚を抱きやすくなります。実際には脳には優先して栄養と酸素が届いていますが、じっとしていて体が冷えたり、足を中心に血の巡りが悪くなったりして、疲労感や眠気が起きやすくなるのです。
こうしたときには、立ち上がって肩を回したり、背伸びをしたり、軽くその場で足踏みやストレッチをするだけで気分転換になります。あるいは階段を一往復する、廊下を早歩きしてくるなど「本格的な運動ではないけれど動いた実感がある行動」が有効です。
体を動かす休憩を定期的に挟むことで、集中の切れ目をリセットし、勉強を続けやすくなります。
勉強に適したおやつの選び方・食べ方

おやつによる糖分の補給が大切である一方、集中力を維持するには、血糖値の急激な変化を避けることも大切です。
甘いジュースやお菓子、ブドウ糖タブレットなどを短時間にたくさん摂ると、血糖値が急上昇した後に急降下し、かえって眠気やだるさにつながることがあります。甘いおやつは特に少量ずつ食べるようにしましょう。
ナッツ類やバナナ、全粒粉クラッカーなどは、食物繊維が多く吸収が穏やかなため、血糖値の急変動が起こりにくいです。また、ガムやグミは、噛むことで眠気を覚ます効果も期待できます。
なお、おやつの量は、中学生なら1日300kcalが目安です。小分けのおやつを選んだり、食べる分だけ小皿に出したりして、食べすぎには注意しましょう。
カロリー消費しても勉強を続けやすい環境づくり
どれだけ意欲があっても、環境が整っていなければ集中を保つのは難しいものです。勉強中のカロリー消費に振り回されず、安定して学習を続けるために、集中しやすい環境づくりも試してみましょう。
集中しやすい環境を整える
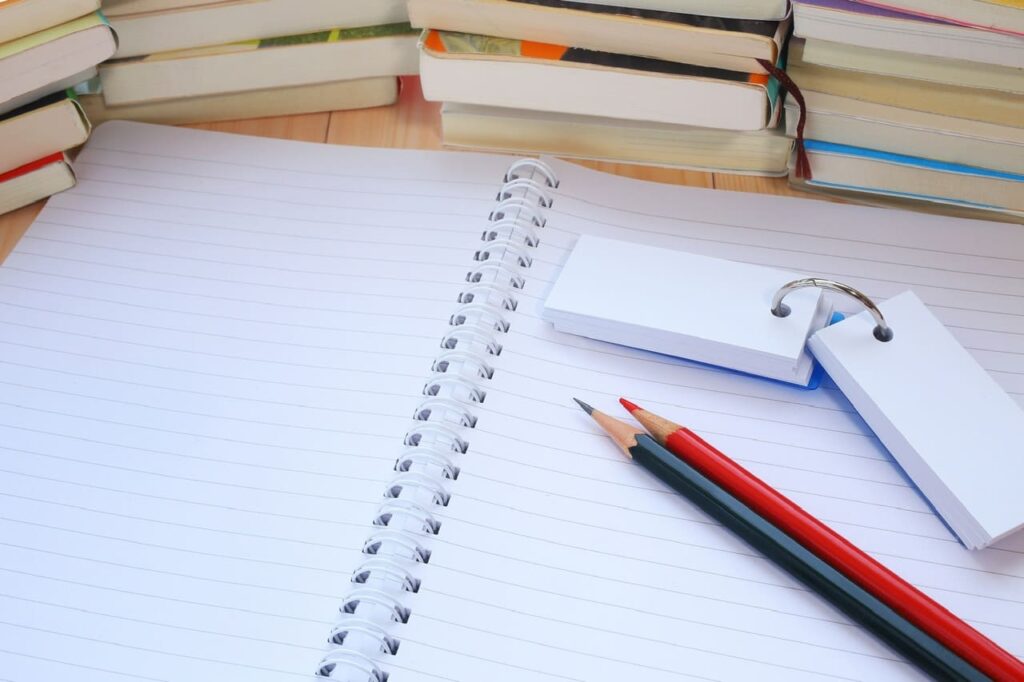
集中力は、意志よりも環境に左右される部分が大きいといわれます。まずは机の上を整理し、今使う教材だけを手元に置きましょう。視界に余分な情報が入らないことで、自然と意識が勉強に向きやすくなります。
また、時間を区切って勉強と休憩を交互に行う「ポモドーロ・テクニック」も効果的です。25分集中+5分休憩を1セットにすることで、脳の疲労をためにくく、集中のリズムを保てます。
さらに、1日の勉強の最初に「今日の目標」や「今日の時間割」を書き出すと、目的意識を持って取り組めます。やる気が続かないときは、環境面の工夫から見直してみるのがおすすめです。
オンライン学習の活用もおすすめ

1人や友人同士ではなかなか集中が続かない場合、オンラインの活用もおすすめです。オンライン家庭教師を利用すれば、家にいながら講師のサポートを受けられ、計画的に学習を進められます。マンツーマンの指導で理解度に合わせたペース配分ができるため、無理なく集中を維持しやすい点も魅力です。
また、最近はオンライン自習室のように、画面越しで他の生徒と一緒に勉強するサービスもあります。仲間の存在を感じることで適度な緊張感が生まれ、ダラダラしにくくなります。自宅学習でも集中のリズムをつくりたい方におすすめです。
まとめ

勉強とカロリー消費の関係について、深掘りしてお伝えしました。2時間集中して勉強しても、脳のカロリー消費は飴玉1個分、体全体でもおにぎり1個分程度です。それほど多くはなく、間食で簡単に相殺されてしまいます。
しかし勉強で空腹を感じるのは、自律神経の切り替わりや、血糖値の低下による自然な反応です。お腹が空く感覚に惑わされず、間食や集中力をコントロールするには、以下の工夫をしてみましょう。
- こまめに体を動かしてリフレッシュする
- 強めの運動で、脳への乳酸(エネルギー源)の供給を図る
- おやつの選び方と食べ方で、血糖値の急変動を避ける
- 集中しやすい学習環境を整える
もし1人での学習継続が難しいと感じたら、当サイトを運営するオンライン家庭教師GIPSでもご相談に乗ります。計画的な学習サポートや集中力を高める環境づくりについて、専門的なアドバイスで力になりますので、お気軽にご連絡ください。
参考文献:
Christopher W. Kuzawa, et al. (2014). Metabolic costs and evolutionary implications of human brain development. PNAS, 111(36), pp.13010–13015.
Raichle, M. E. (2011).The restless brain. Brain Connect, 1 (1), pp.3-12.
健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023|厚生労働省
William H Neumeier. et al. (2016). Exercise following Mental Work Prevented Overeating. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(9), pp.1803-1809.
オンライン家庭教師GIPS
授業のフォロー、志望校対策など、1対1で受講できるオンライン家庭教師。
月額1万円台とリーズナブルで、勉強が苦手な生徒から難関校志望の生徒まで幅広く対応。
- あなたにピッタリの講師がマンツーマンで指導
- 授業のフォロー、志望校対策などにも対応
- 24時間LINEで質問し放題(入会者は何度でも無料)
1回60分の無料体験授業も実施中。
入会費や退会費もありませんので、お気軽にお問い合わせください。