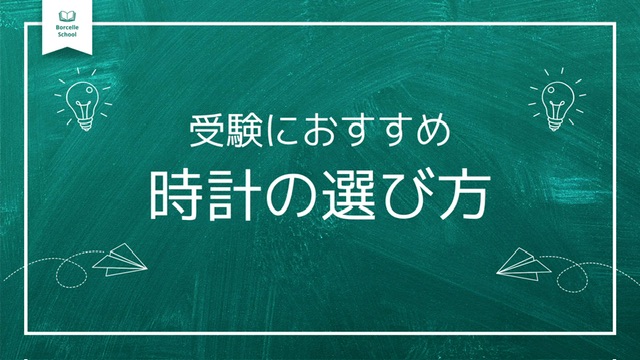試験本番を成功させるためには、準備と道具選びが大切です。特に「時計」は、試験時間の管理に欠かせない重要なアイテムです。 「教室に時計があるから大丈夫でしょ?」と思われるかもしれません。
しかし、時計がない会場や、壁掛け時計が見えづらい席になる可能性もあります。そのため、受験生にとって腕時計は必須アイテムです。
今回のコラムでは、適切な時計選びについて詳しく紹介。試験当日の「腕時計と時間配分のテクニック」も解説します。
受験に時計は必要?

中学受験・高校受験・大学受験において、学校が禁止していない限りは、時計(腕時計)は必要です。受験会場での時計の重要性について、まずお話しします。
試験会場に必ずしも時計があるとは限らない
実は、すべての試験会場に時計が設置されているわけではありません。また、設置されていても以下のような状況があります。
- 座席の位置によって時計が見えない
- 時計の針が見づらい、時刻が不正確
- 古い時計で秒針がない
このような状況では、時間配分が難しくなり、焦りやストレスを感じてしまいます。各学校の規定にもよりますが、腕時計があれば安心です。
でも、時計をそもそも持ってこなかった、忘れてしまった!時にはどうしたらいいのでしょうか。
受験で時計を忘れた・持ってない時の対応

試験当日に時計を忘れてしまった場合、「どうしよう」と焦らず、とりあえず落ち着いて最善策を考えましょう。
①学校(試験会場にいる先生)に相談してみる
試験会場に到着し、時計を忘れたことに気づいた場合には、受付で相談してみましょう。時計の貸出を行っている学校もあります。また、近くのコンビニなどで購入するよう案内されたというケースも。特に対応していない学校もありますが、とにかく落ち着いて、受付や案内をしている先生などに状況を話してみましょう。
②問題数やページ数で時間配分の目安をたてる
1ページ10分、5問で15分など、試験前に感覚的なペース配分をおおよそたてておきます。日頃から、時間配分を意識して、過去問を何度も解いていると、自然と「時間配分の感覚」が身につきます。

でも、正確な時間管理としては、やはり腕時計がないと不安かもしれません……。
事前の準備で、必要な持ち物を揃え、忘れないようにするのが大前提です。
どのような時計が良いのかを説明しますので、参考にしてくださいね。
受験に持っていく時計は「アナログ・デジタル」どっち?
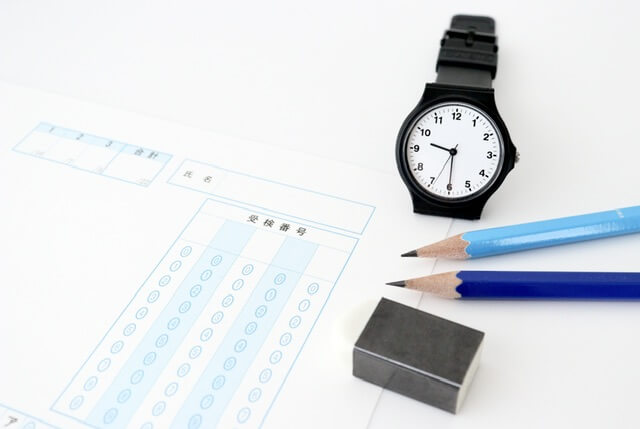
受験用の時計選びでまず迷うのが、アナログ時計かデジタル時計かという選択です。結論から言うと、アナログ時計がおすすめです。
では、なぜアナログ時計がおすすめなのでしょうか?
試験によってはデジタル時計が禁止の場合も
デジタル時計の中には、以下のような機能がついているものがあり、受験では使用できない場合があります。
- アラーム機能
- 電卓機能
- 辞書機能
- 通信機能
特に大学入学共通テストでは、これらの機能がついたデジタル時計は持ち込み禁止となっています。事前に試験要項をよく確認することが重要です。
アナログ時計のメリット
受験では、アナログ時計の方が有利な場面が多くあります。
- 残り時間を視覚的に把握しやすい
- 秒針で細かい時間配分が可能
- 機能がシンプルで試験規則に適合しやすい
- 電池切れの心配が少ない
特に、長針と短針の位置関係から、「あと○○分」という感覚的な時間把握ができる点が大きなメリットです。自分のタイマーとして使いこなせるようになるといいですね!
時間管理の精度が合否を分ける
受験では、問題ごとの時間配分が非常に重要です。アナログ時計なら、秒針を活用して以下のような管理ができます。
- 難しい問題に予定以上の時間をかけないよう管理
- 見直し時間の確保
- 解答順序の調整
デジタル時計では数字での表示のみですが、アナログ時計なら円形の文字盤で時間の流れを直感的に感じられます。視覚的な情報は、プレッシャーがかかる試験中でも冷静な判断を助けてくれます。
アナログ時計なら、何でもOKというわけではありません。次に「NGの時計」について解説します。
受験(試験)にふさわしくない時計とは?「ダメ」なケースを知ろう

受験で使用できない時計の種類を知っておくことは、トラブルを避けるために重要です。
音が鳴る時計は絶対NG
音が出る機能がついた時計は、試験会場では使用できません。
- アラーム機能
- チャイム機能
- 時報機能
- 操作音がする時計
これらの音は他の受験生の迷惑になるだけでなく、不正の疑いをかけられる可能性もあります。事前に設定を確認し、必要に応じて機能を無効化できる時計を選びましょう。
スマートウォッチは基本的に禁止
最近人気のスマートウォッチは、以下の理由で受験には使用できません。
- 通信機能がある
- 計算機能がある
- 電子辞書機能がある
- カンニングに利用可能な機能が多い
シンプルな時計機能のみのモードがあっても、試験監督からは判断が難しいため、避けるのが無難です。
その他の禁止例
試験によって異なりますが、以下のような時計も使用できない場合があります。
- 大きすぎる時計(文字盤が規定サイズを超える)
- 高級ブランドの装飾が派手な時計
- 電卓機能付き時計
- 蓄光(暗闇で光る)機能が強すぎる時計
受験での時計選び「保護者が事前にチェックすべきポイント」


高校生くらいになれば任せられそうですが、それでも念の為、第三者の目で確認してあげてください。
小学生や中学生ならなおさら、腕時計選びや準備も親の手助けが必要ですよ。
- 試験要項で規定を確認
- 実際に持参する時計で模擬試験を受ける
- 電池残量を確認
- 時刻合わせの方法を確認
特に重要なのは、試験要項の確認です。中学受験では、そもそも腕時計が禁止のところもありますし、高校受験でも細かい規定のある学校も少なくありません。
2025年の募集要項を見ると、以下のような記述があります。
ー東海中学校 入学試験案内
持ち込み禁止品 分度器・三角定規・マーカーペン・計算機能/通信機能を備えた物品 腕時計を持ち込んでも構いませんが、スマートウォッチ等の通信端末の持ち込みは禁止します。
引用:東海中学校 東海高等学校公式サイト
大学入試センターでは、腕時計の質問に対し、以下のように回答しています。
Q8 試験時間中に使用できる時計はどのようなものですか。
A8 時計として使用できるものは計時機能だけのものです。辞書や電卓等の機能があるもの、秒針音のするもの、大型のものは使用できません。また、スマートウォッチ等のウェアラブル端末、及びキッチンタイマーや学習タイマーは使用できません。ウェアラブル端末については着用することもできません。なお、辞書、電卓、端末等の機能の有無が判別しづらいものを使用していた場合は、解答を一時中断させて試験終了まで預かることがあります。
引用:大学入試センター
大学入学共通テストやそれぞれの中学・高校・大学の入試要項には、持ち込み可能な時計の詳細が記載されています。事前に必ず確認し、不明な点は受験校に直接問い合わせることをおすすめします。
受験におすすめの時計と選び方のコツ
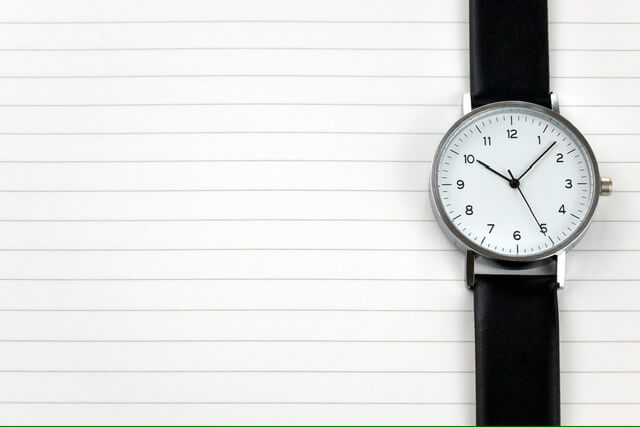
「デジタルよりアナログが良い」「使用できない時計」について説明しました。ここからは、受験に最適な時計選びのポイントを具体的にお伝えします。
シンプルで視認性の高いアナログ時計がベスト
受験用の時計として最もおすすめなのは、以下の特徴を持つアナログ時計です。
- 文字盤が大きく、数字が見やすい
- 秒針がついている
- 白い文字盤に黒い文字(コントラストが高い)
- 余計な機能がついていない
シンプルな時計は、試験規則に抵触する心配がなく、時間管理にも最適です。
選び方の具体的なポイント
時計選びでは、次の点に注目しましょう。
(1)文字盤のサイズと見やすさ
- 直径30mm以上が望ましい
- 数字の表示が大きく明瞭
- 背景色と文字色のコントラストが鮮明
(2)秒針の有無とその重要性
- 秒針があると細かい時間管理が可能
- 秒針の動きがスムーズ(カクカクしない)
- 秒針の色が分針・時針と区別しやすい
(3)ベルトの素材と快適性
- 革製やナイロン製が適当(金属製は音が気になる場合も)
- 長時間着けても疲れない軽量性
- 調整可能で手首にフィットする

持っている腕時計でも、禁止なものでなければ大丈夫。もし新たに購入するなら、上記のポイントを抑えた、信頼できる国産のリーズナブルでシンプルな時計を選んでくださいね。
事前準備で安心を確保
受験当日のために、以下の準備をおすすめします。
予備時計の準備
- 同じタイプの時計を2つ用意
- 片方は予備としてカバンに入れておく
- 電池交換は受験2週間前までに済ませる

予備まで用意しなくても…と思うかもしれませんが、たとえば会場への移動中に何らかの理由で故障や紛失をしても、カバンに予備があれば安心です。
まったく同じ時計でなくても、予備は条件になるべく近い格安なものや、親が使用しているものでもいいと思います。
模擬試験での動作確認
- 実際の試験時間で着用
- 違和感がないか確認
- 必要に応じて調整
普段、腕時計をしていないと、意外と気になるものです。模試や塾内テストの時などに、実際に使用する腕時計をして、時間配分にどう使うかを慣れておくと安心です。

時計のような小さな準備も、合格への大切な一歩ですよ!
時計があることで、試験の時間配分がやりやすくなります。最後に、試験における時計の活用法についてお話しますね。
受験での腕時計の活用法「時間配分テクニック」
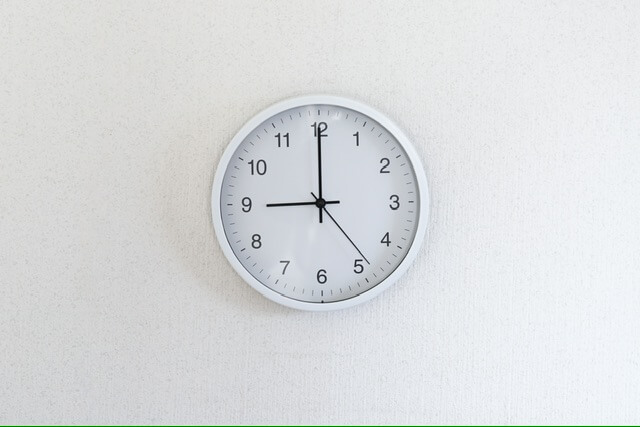
時計があっても、効果的に使えなければ意味がありません。ここでは、アナログ時計を使った実戦的な時間管理テクニックをご紹介します。
① 試験開始時に「長針がどこにあるか」を覚える
試験が始まったら、まず長針(分針)の位置を確認して記憶しましょう。
例)開始が9時の場合
- 長針は「12(0分)」を指している
- 終了は10時(長針が再び12に戻る)
- つまり、長針が1周したら試験終了
この方法なら、「あと何分」と細かく計算する必要がなく、長針が1周すると自然に終了時間がわかります。普通の時計の読み方ができれば、どんな受験生でも使える簡単なテクニックです。
他の例)11時30分開始の場合
- 長針は「6(30分)」を指している
- 終了は12時30分(長針が再び6に戻る)
- 長針が6から始まって6で終わる
② 問題を「何分でやるか」を事前に決めておく
試験前に、各設問にかける理想の時間配分を決めます。長針の位置を目標として設定することで、視覚的に進捗を管理できます。
例1)60分の試験、大問が4つの場合
- 1つの大問につき約15分ずつ配分
- 長針の目標位置:「3」「6」「9」「12」
- 長針が「3」に来たら大問1を終えて大問2へ
- 長針が「6」で大問2を終えて大問3へ
- この調子で進めていく
例2)90分の試験、大問が3つの場合
- 1つの大問につき約30分ずつ配分
- 長針の目標位置:「6」「12」「6」(開始位置に戻る)
- 各大問で長針が半周する時間を使う
初心者向けのヒント
「分単位で考えると難しい」という人は、長針の位置だけに注目して「今、長針はどこ?」と確認するだけでOKです。
見直し時間の確保や、ペースを判断するのにも、腕時計が活躍します。ただし、大切なのは「長針や秒針のあるアナログ時計を見て、時間を判断するのに慣れておくこと」です。
デジタル時計やスマートウォッチ、スマホで時間を見ている子がほとんどです。
模試はもちろん、過去問を家庭で行う時も腕時計をして時間のチェックをしながら解くことを繰り返し、十分に慣れておきましょう。また、塾や家庭教師の先生にも、時間配分と腕時計の見方について教えてもらいましょう。
まとめ
受験時計選びの5つのポイント
1. アナログ時計を選ぶ(デジタルは禁止の場合あり)
2. シンプルで見やすいデザインを重視
3. 秒針付きで正確な時間管理を実現
4. 予備時計を準備して万全の体制に
5. 模試で実際に使用して動作確認する
腕時計を選んだら、もっとも大切なのは「実際に模試や過去問でも腕時計をして、時間配分のやり方に慣れる」ことです。
時間に支配されるのではなく、時間を管理すると考えましょう。知り合いの子は、腕時計を持って神社に行き「この時計でうまくいきますように」とお願いしたそう。持っていることが「お守り」になる、そんな風に考えるのもいいなと思いました。 皆さんの受験がうまくいくように、願っています!
編集:オンライン家庭教師GIPS
オンライン家庭教師GIPS
授業のフォロー、志望校対策など、1対1で受講できるオンライン家庭教師。
月額1万円台とリーズナブルで、勉強が苦手な生徒から難関校志望の生徒まで幅広く対応。
- あなたにピッタリの講師がマンツーマンで指導
- 授業のフォロー、志望校対策などにも対応
- 24時間LINEで質問し放題(入会者は何度でも無料)
1回60分の無料体験授業も実施中。
入会費や退会費もありませんので、お気軽にお問い合わせください。